メインメニュー

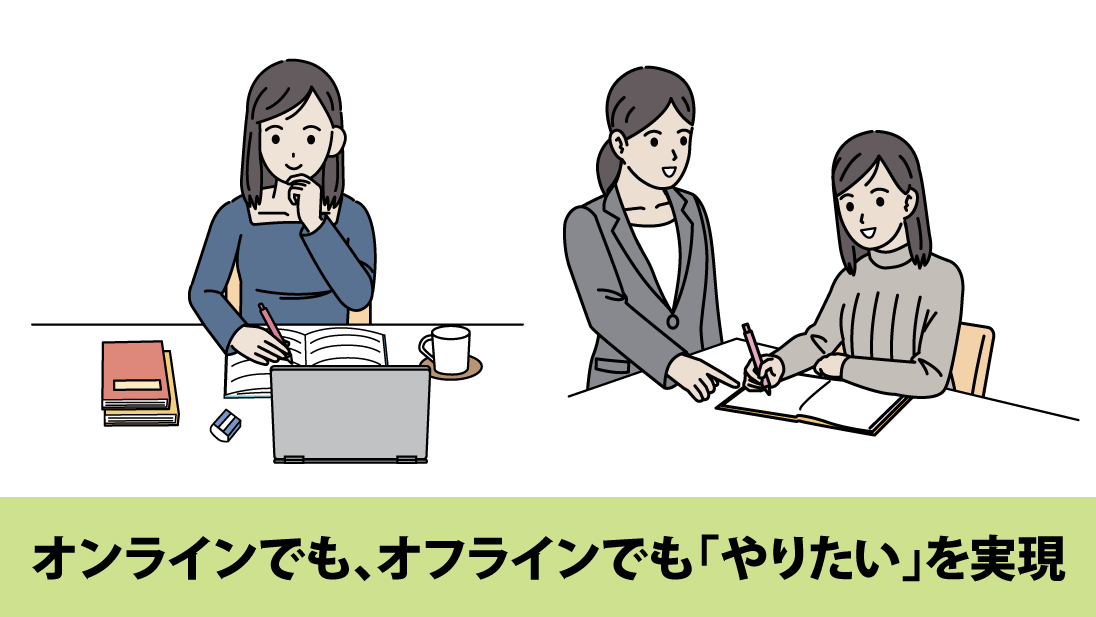
N高等学校・S高等学校・R高等学校では、生徒たちが自分の強みを活かして未知の世界に踏み出し、自分の進路を切り拓いていく「総合力の育成」を目標の一つとしています。
この総合力を身につける手段として、ネットを最大限活用し、未知の世界を知るためのツールとして、また、つながる手段や機会を増やすための手段として扱っています。
ネットを活用した学びであれば、場所や環境に関わらず受講が可能です。たとえば、周囲に外国語に詳しい人がいなくてもネイティブの英語を学べたり、最先端のプログラミング教育を受けられたりするなど、物理的な制約を超えた学習ができます。
さらに、官公庁や大手上場企業などとのコラボレーションによるプロジェクト型学習や、起業部・投資部などのネット部活の活動を通じて、実社会とつながりながら実践的なスキルも身につけられます。
こうしたことが可能なのは、KADOKAWA・ドワンゴの情報発信能力と通信制高校のネット学習システムを組み合わせているからです。ネットという新しい言語を使いこなすことで、生徒たちの可能性は無限に広がり、総合力の獲得につながるのです。
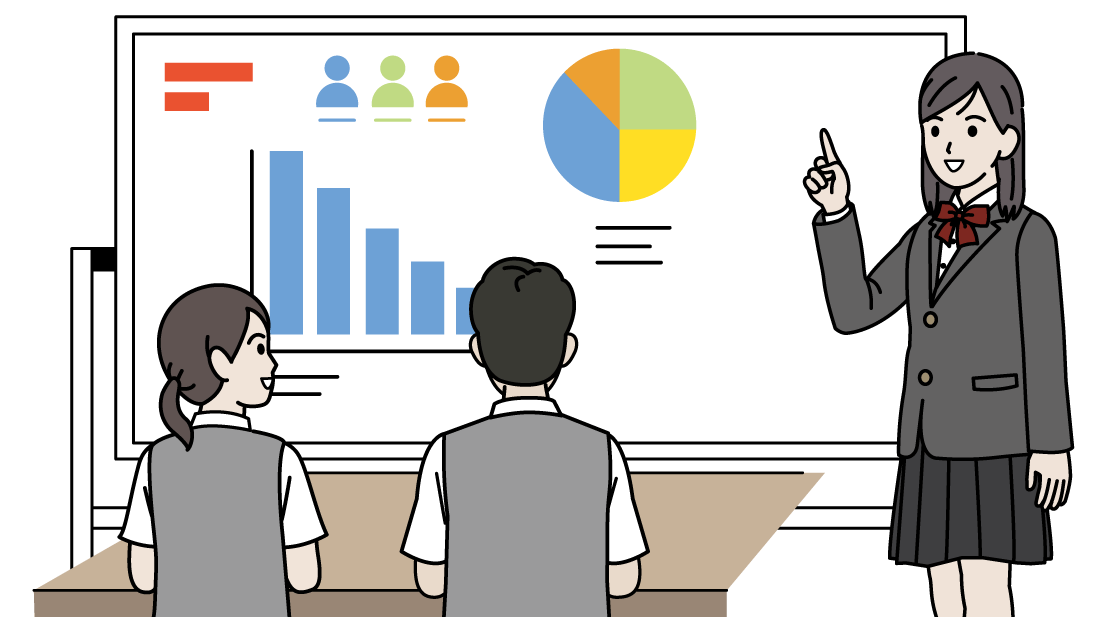
総合力を獲得するために、N高等学校・S高等学校・R高等学校では、「社会で必要だから学ばなければならない」という考え方ではなく、「これをやりたい」という生徒自身の意欲を大切にしています。
対面でのコミュニケーションが苦手でも、ネット上での交流が得意な生徒はいます。イラストやプログラミングなど、特定の分野に秘めた才能があっても、スポットライトが当たる機会が少ない生徒もいます。そのような生徒一人ひとりが本当に輝ける場所を提供し、可能性を広げていくことが私たちの大切な使命だと考えています。
そのために、企業とコラボレーションしたプロジェクト型学習など通して、職業や自分の将来像、世の中についての理解を深めます。一方で、生徒会活動や部活動、放課後の自由時間など、仲間との会話が生まれるような活気ある雰囲気づくりを行い、「普通の学校」としての当たり前の環境も大切にしているのです。
N高等学校・S高等学校・R高等学校の強みは、多様な学びの手段を用意し、生徒の選択肢を増やしながら成長を見守ることです。特に大切にしているのは、ただ機会を提供するだけでなく、生徒自身の「これがしたい」という目標から「どうしたらそれが実現できるか?」を一緒に考えるプロセスです。例えば、過去のディベート同好会では、大会参加のための仲間集めや出場資格取得の方法を自分たちで考え、自分たちの力で全国大会入賞という実績を獲得しました。
これこそが、生徒の「やりたい」に寄り添うN高等学校・S高等学校・R高等学校のアプローチです。
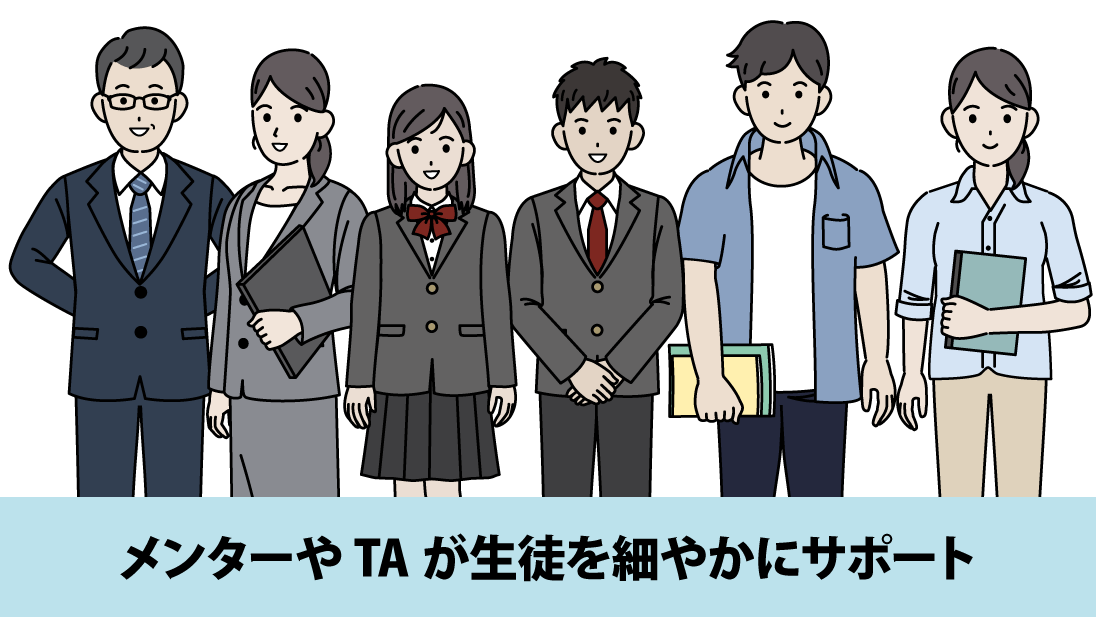
生徒の成長を支えるのは「メンター」と呼ばれる教職員たちです。従来の「担任」とは違い、生徒の自主性を尊重しながら伴走する存在です。
N高等学校・S高等学校・R高等学校では、一人の生徒に複数のメンターがついています。担任にしか相談できないという環境ではなく、生徒自身が興味関心や内容に応じて相談できる体制を整えています。こうした柔軟な関係性が、多様な個性を輝かせることにつながっているのです。
また、生徒が「何かをやりたい」と思ったとき、その実現に向けて必要なプロセスを示したり、学校外の実社会で活躍する専門家や企業など、つながるべき人と橋渡しする役割も担っています。このように実社会とつながる学びを提供できることが、N高等学校·S高等学校·R高等学校の取り組みの特徴です。
さらに「TA(ティーチング・アシスタント)」も大切な存在です。主に大学生が務めるTAは、大学生活の話を聞けるだけでなく、年齢が近いため気軽に相談しやすく、「歳の近い先輩に話を聞くことで、自分の近い将来が見える」というメリットがあります。TAはメンターと生徒をつなぎ、生徒たちの日々の学校生活のモチベーションを支えています。
この手厚いサポート体制のもと、生徒たちは自分の興味に合わせた学びを深め、時に失敗しながらも自分の強みを活かせる道を探っていきます。この過程で身につく柔軟性や適応力こそが「総合力」なのです。
社会や働き方は日々変化しています。この先に必要な力は、一つの正解を導く力ではなく、変化に対応できる「総合力」です。N高等学校・S高等学校・R高等学校は、柔軟に対応できる力を育む環境を提供しています。